最終更新日: 2020/06/29 11:02 【書き方例あり】美術の鑑賞レポートって何を書くべき?まとめ方やポイントも紹介!
美術のレポートは、どのような書き方にするべきか悩んでいませんか?理科や数学と違い明確な答えのない美術は、どのような着眼点とセンスで感想を書くのかが重要になります。ここでは、美術のレポートを書く際のコツや、気を付けたいポイントを紹介します!参考にしてくださいね。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
【まとめ方】美術レポートの書き方とは?
①美術品に対する感想や意見をメインに書く

1つ目は、美術品に対する感想や意見をメインに書くまとめ方です。美術のレポートは、美術品を見た際に感じた感想など、個人的な意見をまとめるのがおすすめです。美術は理科や数学と違い、明確に正しい答えがありません。個人のニュアンスを含んだまとめでもOKです。
美術品を鑑賞した際、自分はどのような気持ちになったのか、どういった感情を抱いたのかを具体的にまとめましょう。単に「綺麗だった」ではなく「大胆な色使いに作者のこだわりを感じ、綺麗だと思った」のように、具体性のある意見がポイントです。
②美術品に関する歴史的背景などを調べる

2つ目は美術品に関する歴史的背景などを調べるまとめ方です。絵画や彫刻などの美術品には、それぞれに歴史があります。単に見て感じた意見だけでなく、その作品はどういった歴史の中で生まれたのかを調べるのもおすすめです。
まずは作品名、作者名、発表年などを参考に、文献やインターネットなどで調べてみましょう。その作品が生まれたいきさつなどを調べてまとめると、より中身の充実したレポートになります。
レポートを書く際に書籍やホームページを利用した際は、必ず本のタイトルや作家名、ホームページのURLと言った情報も、参考元として記入しましょう。
③美術品から得た知識や興味についてを書く

3つ目は美術品から得た知識や興味についてを書くまとめ方です。美術品を鑑賞して抱いた感想だけでなく、どういった知識が得られたかもまとめのポイントとなります。歴史的背景や作品を作る際の技術など、得た物の内容をまとめましょう。
また、一つの作品を見たことで興味の湧いた物事をまとめるのもおすすめです。作品のジャンル、その作家が発表した別の作品など、新たに調べてみたくなった美術品についてを、書いてみましょう。
【構成】美術レポートの書き方とは?
①鑑賞するきっかけを書く
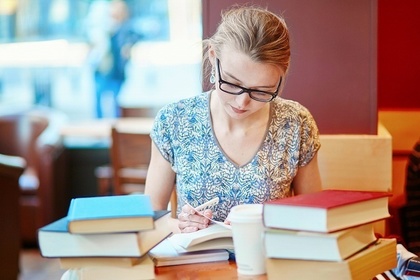
1つ目の構成は、鑑賞するきっかけを書くことです。学校の指定で特定の美術品や美術館を鑑賞する場合は必要ありませんが、自分で作品を選んだ場合は、何故それを観賞しようと思ったかを書きましょう。
作品そのものに惹かれた、作者に興味があった、見たことのないものだから知りたくなったなど、その作品を選んだ理由をまとめましょう。最初の構成できっかけを書くことで、次の構成をまとめやすくなります。
②実際に鑑賞した時の感想などを書く

2つ目の構成は、実際に鑑賞した時の感想などを書くことです。最初の構成できっかけを書いたら、次はレポートのメインである感想、意見などをまとめます。観賞した時の気持ちを素直に書きましょう。
この時、中学生の場合は感想のみでも十分です。しかし、高校生や大学生の場合は、感想プラス美術品の歴史、作者の生い立ちと言ったものを調べて書くと、より内容の濃いレポートに仕上がります。
③まとめの文を書く

3つ目の構成は、まとめの文を書くことです。最後の構成では美術鑑賞に関するまとめ文を書きます。2つ目の構成で書いた感想などから、どういった結論になったのかをまとめましょう。
例えば感想の構成で「戦争の時代に描かれた作品ならではの迫力、恐ろしさを感じた」と書いた場合、まとめ文では「美術品はその時代に起こった出来事や世相を反映していると感じた」というように、締めに持って行くのがポイントです。
美術レポートの書き方でNGのポイントとは?
①箇条書き形式で書く

![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_SP_2-240e63b87945455ba3ae508044064d8f17d376f81b649e0f13fd69dc6e5c5e77.png)








